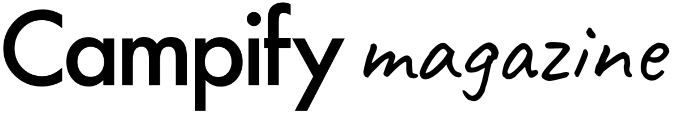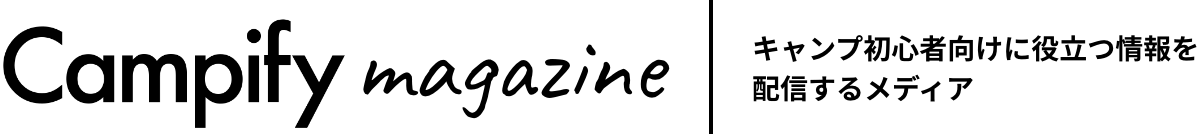キャンプの虫除け対策と最強おすすめグッズをご紹介
自然の中で楽しむキャンプ。山や海の近くのキャンプ場は日常では味わえない、魅力的なアクティビティを数多く体験出来ます。
それと同時に、普段の生活とは違った自然ならではのこともあります。
そう、「虫」です。虫対策無くして楽しく安全なキャンプはできません。
キャンプやアウトドアに興味あるけど、虫がいるから行きたくない…。ご家族やお友達にそう言われた事、ありませんか?
虫と言ってもカブトムシやクワガタではなく、見た目がグロテスクなくらいまだいい方で、刺されたら痒くなったり痛かったり。毒を持っている虫に刺されたら大変ですよね。
虫に刺されない、寄せ付けない対策や、万が一毒を持つ虫に刺されてしまった場合の対処法をご紹介します。
キャンプ場によくいる虫

主にキャンプは夏から秋にかけてがハイシーズン。まさに虫の盛んな行動時期とぴったりマッチ。
まずはどんな虫がキャンプ場には潜んでいるのからお伝えしていきます。
キャンプ場に潜む虫①蚊

キャンプ場にかかわらず日本中どこにでも生息していて、いわゆる「虫刺され」と言ったら一番に思いつくのが蚊です。
蚊はメスのみが吸血を行い、主に水のあるところに発生します。キャンプ場で言えば池や沼などの近く、雨水が溜まってそうな所。例えば壊れた雨どいや遊具の陰のあたり。排水溝などの近くでは発生率がアップします。
気温25℃〜30℃ぐらいで活発に活動し、汗に含まれる乳酸や二酸化炭素を察知して近づいてきます。
蚊に刺されやすいと言われる人とは?
・赤ちゃん、又は子供
・妊娠している女性
・汗かきの人
・お酒を飲んでいる人
・黒い服を着ている人
など
基本的に体温が高めの人(とき) と言われています。
キャンプ場に潜む虫②ブヨ
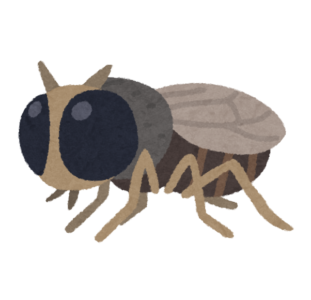
蚊は人の皮膚に針を刺して吸血するのに対し、ブヨは皮膚を小さく噛み切って出てきた血を吸って餌にします。ここだけを聞くともう悪魔ですね(笑)
ブヨもまた水の近くに生息しますが、渓流などの綺麗な水の近くにいます。気温は比較的低く涼しいくらいの日、朝や夕方に遭遇する場合が多いと言われています。
症状としては、刺された直後は蚊ほどの強烈な痒みはないものの、幹部が赤く腫れ、1〜2週間ほど痒みや痛みが続く場合もあり、発熱の症状が現れることもあります。
キャンプ場に潜む虫③ハチ

キャンプ場で遭遇する最も恐ろしい虫の1つと言えばやはり蜂。国内でも年間数千件の被害が報告され、死亡事故に繋がる事例も毎年平均20件ほど報告されています。
蜂には細かく分けるとかなりの種類があり、日本中に生息しています。中でも遭遇しやすい3種類の蜂を押さえておきましょう。
スズメバチ
日本で一番被害が多く報告されているのがスズメバチと言われています。体長は4cmくらいになり、攻撃性も強く、主に雑木林の中に生息していています。遭遇したら、追い払ったり撃退しようなんて思わずに、まず「そっと逃げる」ことをおすすめします。
アシナガバチ
スズメバチほど凶暴ではないまでも、毒性の強い蜂の一種です。
巣を刺激したり、手で払ったりしない限り攻撃してくることは無いようですが、洗濯物などの中に入り込んでいて、気づかず袖を通して刺されるなどのトラブルが多いようです。
ミツバチ
蜂の中ではおとなしい種類ではありますが、やはり刺激すると攻撃してきます。刺されるとミツバチの体から針が抜け、人の皮膚に針が残ります。この針を抜かないといつまでもチクチクした感じが残るので、ピンセットで針を抜き、中の毒をしっかり出しながら洗浄しましょう。
キャンプ場に潜む虫④毛虫
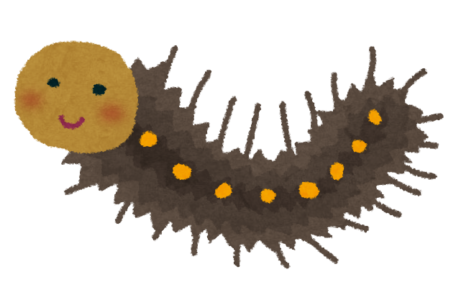
毛虫と呼ばれるほとんどが蛾や蝶の幼虫です。稀に毒を持っていて刺す種類もあるようですが、よく見かける毛虫の中にはほんの数種類のみだそうです。とはいえ、私も小さい頃に刺された嫌な思い出があります。
毛虫は6月〜8月が発生のピークで、主に木の葉などの植物に寄生しています。キャンプ場でテントを張る際は、林間のサイトには要注意です。
キャンプ場に潜む虫⑤マダニ

引用:アース製薬公式サイト
マダニは鹿や、イノシシなどの哺乳類の野生動物に寄生している虫です。ですので、野生動物が通る可能性のある自然豊かなキャンプ場に生息していることがあります。
マダニは血を吸うだけでなく、感染症を媒介することでも有名です。
またマダニに血を吸われても、蚊のようにご自身で潰さないでください。
吸血中のマダニを下手に取り除こうとすると、マダニの体の一部が皮膚の中に残ってしまい化膿してしまうこともあります。
もしマダニに咬まれているのを見つけたら、すみやかに皮膚科等の病院でマダニの除去や消毒など適切な処置を受けてください絵は。
マダニ対策に関しては、国立感染症研究所さんのマダニ対策パンフレットに詳しく記載されています。
是非一度ご確認ください。
https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/2287-ent/3964-madanitaisaku.html
また、ワンチャン等ペットとキャンプを楽しまれる際は、ペットにもマダニが付かないよう気をつけてくださいね。
次のページでは、虫の少ないキャンプ場の立地やおすすめの虫対策をご紹介します。